「RC造って、いまや都市部のマンションでは定番の構造。でも実は、日本でRC造の集合住宅が登場したのは100年近く前って知ってましたか?“頑丈で長持ち”なRC造の歴史を、ちょっとしたトリビアと一緒にのぞいてみましょう。」
1. RC造=今や当たり前。でも昔は…?
RC造とは「鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete)」の略。鉄筋で骨組みをつくり、その周囲をコンクリートで固める構造で、耐震性・耐火性・遮音性など、マンションに求められる機能を高水準で満たしています。
いまや新築マンションの大半がRC造。ですが、その普及には長い年月と社会の変化がありました。最初は高嶺の花だったRC造は、どうやって“当たり前の住まい”になったのでしょうか。
2. 戦前〜戦後すぐのRC建築(同潤会アパートなど)
日本でRC造の集合住宅が最初に登場したのは1920年代。関東大震災を受けて設立された「同潤会」が、その先駆けとなりました。
代表的なのが「同潤会青山アパート」や「上野下アパート」など。鉄筋コンクリート造で建てられたこれらの建物は、災害に強く、当時の最新設備(水洗トイレや共同浴場など)を備えたハイカラな住まいでした。
当時の庶民からすると「未来の住まい」そのもの。ですが建設コストは高く、RC造はまだ一部の都市高級住宅に限られた存在でした。
3. 高度経済成長期と団地ブーム
1950年代後半からの高度経済成長により、都市部には人口が急増。住宅不足の解消を目的に、国と地方自治体は大量の住宅供給を行いました。
ここで本格的に登場したのが、RC造の団地です。プレキャスト工法(あらかじめ部材を工場でつくる)やモジュール設計を取り入れることで、短工期・低コストで大量供給が可能に。
この時期に建てられた「公団住宅(現UR)」「県営住宅」などの多くがRC造で、日本全国に“コンクリートの箱”が広がっていきました。とくに郊外のニュータウンに並ぶ団地群は、当時の住宅政策の象徴ともいえます。
4. バブル期~現代のRCマンション進化
1980年代のバブル景気で住宅ニーズが多様化すると、RC造マンションはさらに進化を遂げます。
高級志向・都市志向に合わせて、内廊下設計・免震構造・設備のグレードアップが進みました。タワーマンションブームもこの時期にスタート。RC造はそのまま超高層マンションの土台にもなっていきます。
さらに2000年代以降は、省エネルギー性や環境配慮も加わり、断熱性の向上や太陽光発電の設置なども一般化しました。
近年では「制震装置付きRC造」や「スマートマンション」といった、技術とライフスタイルが融合した建物も増えており、まさに“暮らしとともに進化する構造”といえるでしょう。
5. RC造ならではの歴史的トリビア
ここで少しRC造にまつわる雑学を。
●「RC造は永久に持つ」はウソ?
RC造は「100年住宅」とも言われますが、実際には設計耐用年数は60年前後。もちろん、定期的なメンテナンスをすればそれ以上使えますが、老朽化が進んだ建物は建て替えや大規模修繕の対象となります。
●建て替えができない理由
実は古いRCマンションほど建て替えが難しいんです。なぜなら、区分所有権という制度のもと、住民の5分の4以上の合意が必要になるから。加えて、建て替え時の費用や仮住まいの問題など、超えるべきハードルは少なくありません。
●取り壊された“伝説のRC”
かつて青山にあった「同潤会青山アパート」は、長く愛されながらも老朽化のため2003年に取り壊され、「表参道ヒルズ」へと生まれ変わりました。時代を超えたRC造の建物が、新たな都市の景観へと繋がるのもまた面白い点です。
6. まとめ:RC造は時代とともに進化してきた“暮らしの器”
RC造マンションの歴史をひもといてみると、それは単なる建築技術の進歩だけでなく、日本人の暮らし・経済・価値観の変化そのものでもあります。
「安心して住める」「長く使える」「資産価値がある」──そうした期待とともに、RC造は時代ごとのニーズを取り込みながら進化を続けてきました。
今では当たり前の存在となったRC造ですが、その背景には多くの試行錯誤と社会の動きがありました。あなたの住むそのマンションにも、知られざる“物語”があるかもしれません。
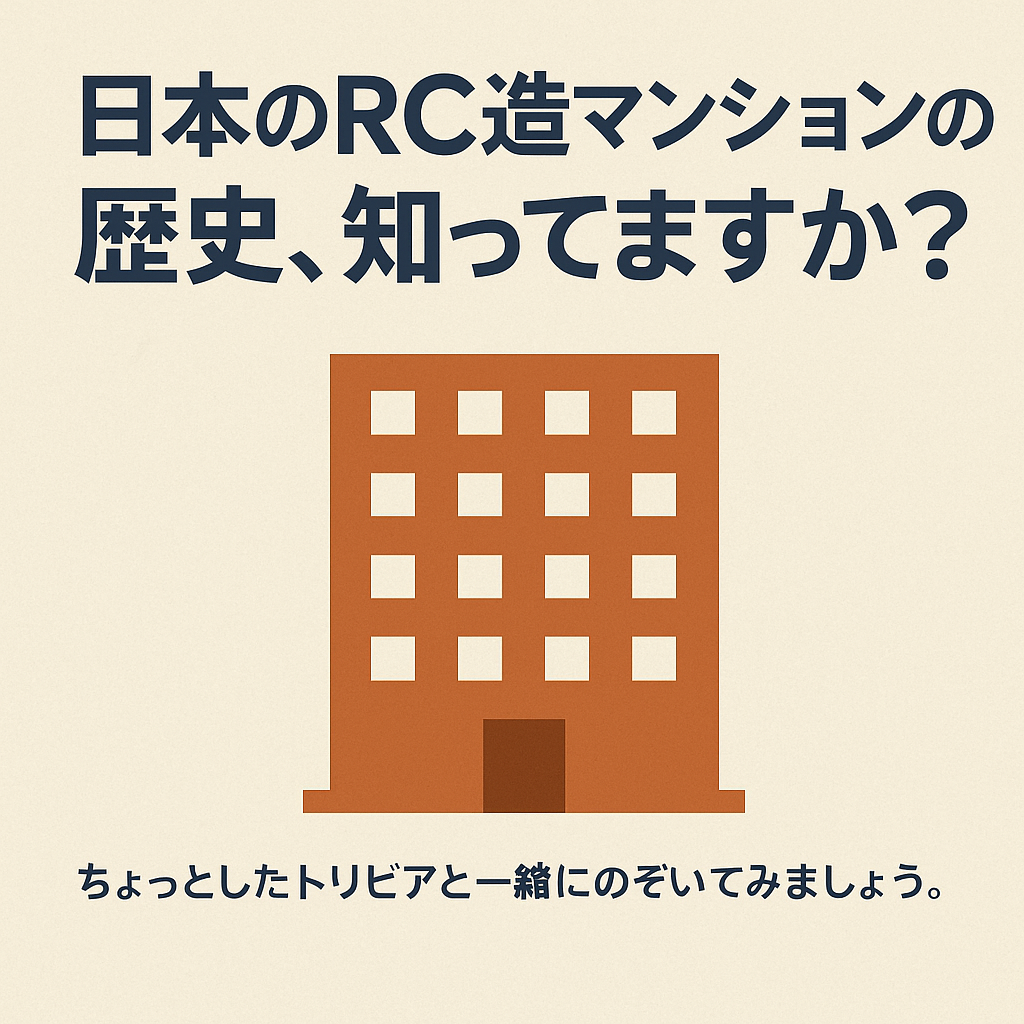

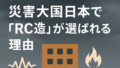
コメント